離れている間に培ったこと ひきこもり先生 ぼっち・ざ・ろっく ブルーロック silent
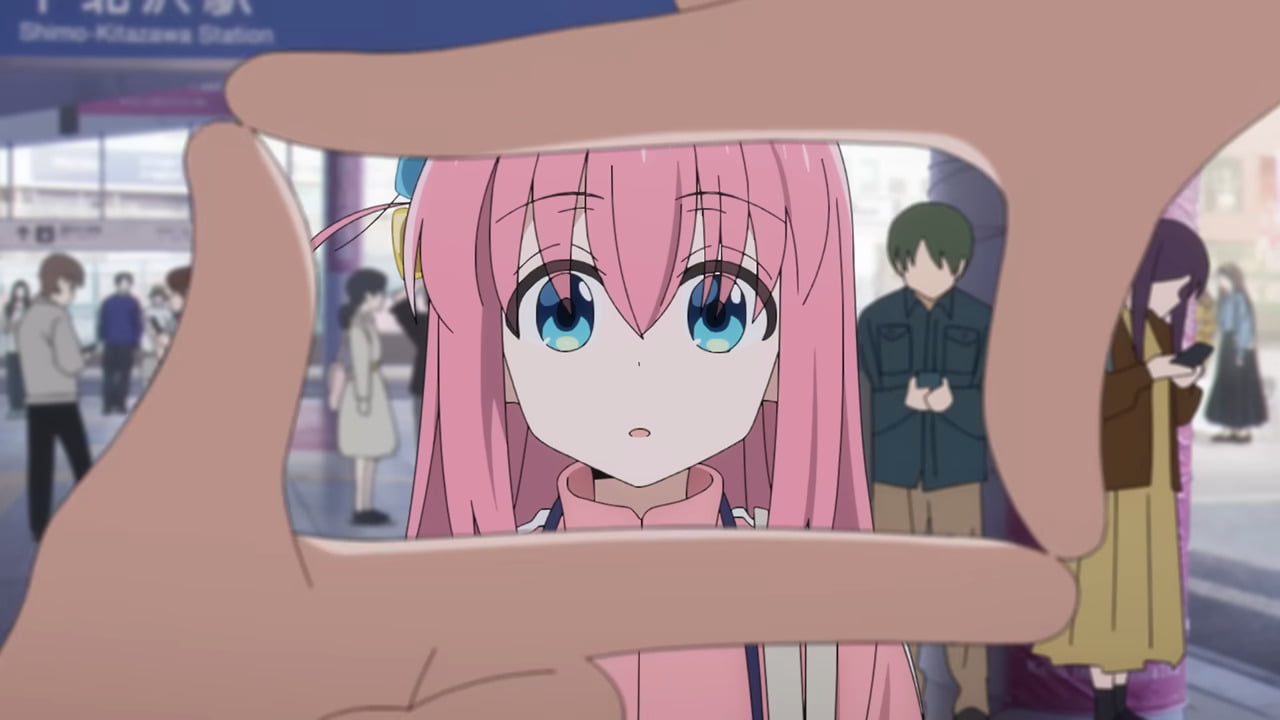 |
| (TVアニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」第2弾PV - YouTube) |
離れていること ひきこもり先生
元ひきこもりの上嶋陽平(佐藤二朗)は、非常勤講師として梅谷中学校に2年ぶりに復帰。不登校生徒が集まるステップルームの他に3年A組の副担任サポートも担うことになった。着任早々、近くで起こったホームレス襲撃事件に梅谷中学校の生徒が関わっていたことが判明。職員室は修学旅行を自粛するかどうかで揺れていた。そんな中、陽平は修学旅行の準備に熱心だった松田篤人(寺田心)を励ますのだが、逆に篤人は陽平に反発する。
前編「どうでもよくない!」 - ひきこもり先生シーズン2 - NHK
言いたいことは我慢しないで言っていい、と訴える陽平(佐藤二朗)に、生徒たちは「やっぱり修学旅行に行きたかった」と本音を明かす。陽平は修学旅行を復活させるために、教育委員会の西村(室井滋)や、元校長の榊(高橋克典)の励ましを受け、保護者会の説得に挑む。一方篤人(寺田心)の母親冴子(高橋由美子)が病気だと知った藍子(鈴木保奈美)は冴子に介護支援を受けるように説得するがなかなか聞き入れてもらえずにいた。
後編「言えなかったこと」 - ひきこもり先生シーズン2 - NHK
 |
| (ひきこもり先生 PR動画 - YouTube) |
上嶋陽平は普段は焼き鳥屋をやっているので、学校の近しい人からはヤキトリと呼ばれている。『ひきこもり先生シーズン1』では、様々な問題を抱えていたり押し付けられたりしている不登校の生徒たちの居場所であるステップルームが舞台となっていた。ヤキトリはそこで非常勤講師を任される。彼は不登校の生徒の言わば「普通でない」問題と向き合いながら、彼らを学校へと向かわせ、自身のひきこもりの過去にも向き合っていく。『シーズン2』では趣きが異なり一般のクラスに焦点が当たる。コロナ禍で皆マスクをしており、学校での活動も様々な制限を受けていて、生徒たちは皆何らかの我慢を強いられている。そんな中である逆転が起こる。普通教室の生徒たちはコロナ禍で我慢をしていてそれを普通として受けとめているが、何らかの理由で普通教室にいられなくなったステップルームの生徒たちはそこから抜け出して自由を享受しているのではないか。生徒のなかにはステップルームのいわゆる自由を「サボっているのではないか」と解釈しはじめステップルームの生徒に嫌がらせをするものまで出てくる。普通教室の生徒は我慢の限界に達しているがそれを誰かに言うことができずスケープゴートを探すことしかできない。
普通教室の生徒である松田篤人は母子家庭で暮らしていて、しかも母親は病気で寝たきりである。役所にヘルパーの支援等を申請すればいいのだが、母親は息子の親権を心配して相談しようとせず、篤人は一人で母親の看病をして、いわゆるヤングケアラーとして生活している。彼は他の生徒より明らかに大変な生活をしている。彼の日常は明らかに他の生徒とは違っているのだが、彼は頑なに自分を普通だと言い張っている。ある日、地元の不良がホームレスの段ボールハウスに放火している現場に篤人は遭遇する。その様子が通行人に撮られSNSに上げられ、篤人は火事の現場に居合わせたことで学校で問題になる。彼は無関係なのだが、その騒動のせいで修学旅行の計画が白紙になってしまう。もともとコロナ禍で保護者の反対や何かあった時の責任論も多く、教師たちは二の足を踏んでいた。篤人はクラスの皆の前で騒動について謝罪する。同時に彼はホームレスの家が燃えていて本心はスッとしていたと正直にいう。ホームレスはサボっているからそういう目にあっても当然だと思ったという。自分は火をつけていないが、火をつけた人間と同じなのだという。ヤキトリは普通教室の生徒たちが我慢をして抱えて抱えきれない気持ちがあるのだと知って、生徒たちに修学旅行を我慢させることをやめさせようとする。
コロナ禍でソーシャルディスタンスという言葉が一種の流行かつ一時的な習慣になった。現在は5類への移行に象徴されるような形で転換が起こっているが、一旦身についた距離の感覚は何らかの形で残るのだろうか。このドラマのなかでは少なくとも二度、人と人との距離に関して不思議なことが起こっている。一つ目はヤキトリが生徒たちの代わりに修学旅行の白紙撤回のため保護者を説得する場面だ。ヤキトリは生徒たちは修学旅行に行きたいという強い気持ちがあり、何としても行かせてあげたいという。保護者のなかには賛成の者もいるが、感染が広まったらどうするとか学校の責任はどうなるとか反対派の意見が強い。この意見交換会は広い体育館で行われていて、生徒たちは途中で体育館の入り口から議論の様子を聞いている。ヤキトリは拙い表現で生徒たちに気持ちがあるんだという。しかし、その気持ちは体育館の入り口からこちら側へはなぜか入ってこない。生徒たちは議論が終わるまでずっと入り口で立ち聞きをしているだけだ。生徒たちは保護者つまり自分の親に何も言うことができない。これはなぜなのか。議論の様子を聞いて、生徒たちはヤキトリは自分たちの思いをわかってくれたと感動して感謝する。しかし、本来それを伝えるべき相手は自分の親で、ヤキトリはメディアに過ぎないはずなのだが、なぜメディアに伝えただけでコミュニケーションを終えてしまうのだろうか。生徒と親の間にはほとんど無限のような距離が暗に描かれている。
このドラマの最後にホームレスの皆と生徒たちが交流するシーンがあるのだが、そこでも唐突に親に失業したことを話せなくてホームレスになった若者が出てくる。なぜ親に話せないというシーンを繰り返すのだろう。二つ目は同じシーンの中で、段ボールハウスの放火現場に遭遇した篤人がそのことについて謝る場面がある。篤人はホームレスに謝るのかと思ったら、彼が謝ったのはホームレスの支援をしている団体の代表だった。その代表が篤人と当時現場にいたホームレスに引き合わせるのでもなく、その場面はそれで終わってしまった。その代表はメディアとして生徒とホームレスの間のコミュニケーションを止めているのだろうか。それ以降、生徒たちとホームレスたちとは詳しい話もせずにふわっとした協力関係に移行し、生徒たちもホームレスになった若者も「サボっているわけじゃないんだ」とその地域の大人たちを説得し、疑似修学旅行を成功させる。
対話の理念は、人がすでに知っていないものを見つけ出すことだった。この理念を失って、対話はまさに消え失せようとしている。完全に集団化され、絶え間なくコミュニケーションしている人々は、同時にあらゆるコミュニケーションを放棄せざるをえないだろう。そして自分が窓のないモナドであることを白状せざるをえないだろう。彼らは古代の市民的時代以来、実はひそかにそういうモナドだった。彼らはいま、そのアルカイックな未成年状態にのめり込む。(p145)
『プリズメン』テオドール・W・アドルノ
個か組織か、「わたしはサプライズ派なんだ」 ぼっち・ざ・ろっく ブルーロック
“ぼっちちゃん”こと後藤ひとりは会話の頭に必ず「あっ」って付けてしまう極度の人見知りで陰キャな少女。
そんな自分でも輝けそうなバンド活動に憧れギターを始めるも友達がいないため、一人で毎日6時間ギターを弾く中学生時代を過ごすことに。
上手くなったギターの演奏動画を“ギターヒーロー”としてネットに投稿したり文化祭ライブで活躍したりする妄想なんかをしていると、気づいたときにはバンドメンバーを見つけるどころか友達が一人も出来ないまま高校生になっていた……!
ひきこもり一歩手前の彼女だったがある日“結束バンド”でドラムをやっている伊地知虹夏に声をかけられたことで、そんな日常がほんの少しずつ変わっていく――
INTRODUCTION | TVアニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」公式サイト
 |
| (TVアニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」第2弾PV - YouTube) |
『ぼっち・ざ・ろっく』は直接コロナを描いた作品ではないが、人見知りで頑なに人を避けようとする主人公の後藤ひとりの態度はコロナ禍で人と人との距離が求められた私たちの生活の中の多くの部分と似ている。コロナ禍でマスクをし声を出すことを制限され、人と人との距離を保つように言われ、空間に定員が設けられ、いつもより多くの時間を家で過ごさなければならなかった。それは言わば制度的にぼっちになることを求めるものだったが、ぼっちちゃんのそれは単に引っ込み思案ということもあるだろうが、一部は思想信条的なものである。私たちとぼっちちゃんは同じように自分がパーティーに出かけることを自分の家の中に留めおかれながら夢想していなかっただろうか。
このアニメで描かれるのはパーティーではなくバンド活動である。ぼっちちゃんは一人で旅に出ていたわけでもなく、どこか海外に留学していたわけでもなく、ましてや異世界に行ってきたわけでもない。そこでは世界から隔離されていた(?)ぼっちちゃんが皆から離れている間に得たもの、具体的にはギターを弾く能力が、目覚ましいパフォーマンスを見せたり、それによってバンドを救ったりする。それはしばらくの間ほとんど半強制的にそれぞれの家で離れて生きていかざるを得なかった私たちが、もう一度集まることができた時に、それぞれが何か前とは違うものを持ち寄って別の何かができあがるかもしれないという期待の表現でもあるだろう。もちろん一人で学んだことが全ていい方向には進むとは限らず、陰謀論などを得てしまうということもあるのだけど。
知識社会学的歪曲は方法に根ざしている。その方法は弁証法的概念を分類学的概念に翻訳する。社会的に矛盾に満ちた状況が個々の論理的綱(クラッセ)に収まることによって、社会的な階級(クラッセ)は消滅し、全体の像は協調主義的になる。たとえば、上述の著書の第三章では「発見、発明、計画」という意識の三段階が案出されるが、それが企てているのは、さまざまな時期の弁証法的図式を、人々の間に決定的な対立がなくなった社会化された人間の、よどみなく変わる行動様式そのものとして解釈すること以外の何ものでもない。
「直前の目標を合理的に実現する発明的思考から計画的思考への移行がよどみないものであることは明らかである。どういう種類の見込みがあれば、そして意識的な遠隔操作の射程がどれだけ伸びたら、発明する知性から計画する知性への移行が始まるかは誰も言うことができない。」
こうした、自由主義的な社会から「計画的」社会へのスムースな移行という観念には、この移行を異なる「思考」様式の間の移行として捉える把握が対応している。それによって、歴史的過程はそれ自身のうちで一致団結した社会的な全体主観によって制御されているという信仰が目覚まされる。弁証法的概念の分類的概念への翻訳は実在する社会的権力の諸条件を捨象するが、前述の思考の諸段階はその諸条件に依存している。(p45,46)
『プリズメン』テオドール・W・アドルノ
ぼっちちゃんは体育祭を妙に毛嫌いしていて、一致団結とかいったようなノリがかなり苦手である。彼女は常に学校もライブハウスのバイトも辞めたがっているが、バンドを組みたいとは思っているし、いつも背負っているギターについて誰か話しかけてくれないかなとは思っている。ぼっちちゃんはただのギター好きのように見えるが、行動原理が矛盾しているようにも見える。バンドも複数人で活動する以上、一致団結といったようなノリが求められるだろう。もし仮にぼっちちゃんの性格を個人か集団か、個か組織かといったような二項対立から眺めるなら、見方を間違うだろう。それは間違ったジレンマ、ここではあまり意味のないジレンマである。
ヒトラーもスターリンも、組織をモラル上のジレンマに陥れ、大量殺人が大した罪に思えなくなるように仕向ける術に長けていた。一九三二年のウクライナでは、共産党員たちが穀物の収奪にためらいを感じていたが、やがて目標値が達成できるか否かに自分のキャリアと命がかかっていることに気がついた。ドイツ国防軍の将校たちにしても、ソ連の都市を兵糧攻めにすることに全員が賛成だったわけではない。しかしソ連の民間人と自分の部下のどちらを助けるかという選択を迫られていることに気づくと、答えはおのずと明らかだった。(p322,323)
『ブラッドランド(下)』ティモシー・スナイダー
ぼっちちゃんは文化祭でギターを壊してしまうのだが、両親からYouTubeの広告収入が30万貯まっているから新しいギターを買いなさいといわれる。ぼっちちゃんはバンドに誘われる前にギターヒーローとういアカウント名でYouTuberをしており、それなりの再生回数を得ていた。彼女はギターを買えるという喜びよりも、このお金があればバイトをやめられる気持ちが勝ったが、バイトをやめたいとライブハウスの店長になかなか言い出せない。ぼっちちゃんは店長の誕生日が近いことを思い出して、話しかけられないぼっちちゃんは店長に誕生日プレゼントは何がいいか聞いてくれないとドラムの伊地知虹夏に頼む。店長と虹夏は姉妹である。店長は「いらない」という。ぼっちちゃんは漫画っぽいショックを受けてギターを買いにバンドメンバーと出ていく。彼女たちが出て行ったあとで、店長は「私はサプライズ派なんだ」という。
 |
| (TVアニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」第2弾PV - YouTube) |
ぼっちちゃんもおそらくサプライズ派である。サプライズとは思ってもみないことが起こることである。思ってもみないことというのは、皆が一致団結して全員が全員お互いのことを知って、ルールを決めて、以心伝心、ひとつの目的のために尽くすという間柄のなかではなかなか起きないだろう。一致団結の曖昧な定義に従えば、お互いが考えていることも、これから行おうとしていることも皆知られている、あるいは知っているものとして行動するからである。そのような空間の中でサプライズを起こそうとすれば、他の人々から邪魔者、裏切者、馬鹿扱いされるだけだろう。他人が知っていることしか行ってはいけない。思考様式としては、あの個人か集団かといったジレンマが用いられ、何をするにしても集団を気にせざるを得ず、とても窮屈なのだ。
ただ、バンドに入る前の一人でいたぼっちちゃんについていえば、窮屈さという意味では一致団結の空間にいるのと変わらないように描かれている。彼女は最初にバンドの手伝いでギターの演奏を頼まれたとき、段ボールの箱に入って顔や姿が見られないように演奏していた。それは一致団結の世界観と同じくらい窮屈だったろう。もちろん段ボールの箱なら、そこに穴をあけて顔を出すことができる。ぼっちちゃんがたった一人でいる段ボールの箱の中から顔を出したなら、彼女の存在自体がサプライズだろう。(余談だが、箱の中に人が隠れている形式というのは、ぼっちちゃんのすぐに崩れてしまう顔と相まってお化け屋敷を思い出させる。)そうなれば、ぼっちという言葉に表れるような私一人とみんなといったような一般性は無意味なものとして後退して、バンドの4人で何ができるかに考えが移っていく。バンドといっても、四六時中一緒にいるわけでもなく、一緒に練習できるわけでもなく、本番でしか起こらないパフォーマンスが常にサプライズとして付きまとう。ぼっちちゃんのギターのトラブルとそれをフォローする喜多さんのギターの成長、それに答えてぼっちちゃんの自分でフォローするギターテクニック、どれも本番でしか起こらないことだろう。ただ、ぼっちちゃんはサプライズを意識しすぎた結果、演奏中客席にダイブして誰にも受けとめてもらえず、ただの事故になってしまう。サプライズは常に良いとか常に悪いとかいったタイプの現象ではない。
ちょうど『ブルーロック』というサッカーアニメが同じような事柄を扱っている。
 |
| (TVアニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」第2弾PV - YouTube) |
世界一のエゴイストでなければ、世界一のストライカーにはなれない。日本を W 杯優勝に導くストライカーを育てるため、 日本フットボール連合はある計画を立ち上げる。その名も、“ブルーロック(青い監獄)”プロジェクト。集められたのは 300 人の高校生。しかも、全員 FW(フォワード)。 299 人のサッカー生命を犠牲に誕生する、 日本サッカーに革命を起こすストライカーとは──?
──今、史上最もアツく、最もイカれたサッカーアニメが開幕する
TVアニメ『ブルーロック』公式サイト
 |
| (TVアニメ『ブルーロック』2クール目ノンクレジットOP映像|ASH DA HERO「Judgement」 - YouTube) |
個か組織かというのはサッカーの解説などでもよくいわれるが、そのようなよくあるジレンマをこのアニメは一クールで片づけてしまう。登場人物全員フォワードでブルーロックでの生き残りをかけて、数々の難関をクリアしていくのだが、最初の山場はメンバーを11人ずつに分けて5チームの総当たり戦を行うというものだ。11対11を試合をしなければならないが、彼らは全員フォワードである。誰がキーパーやディフェンスをやるのかということでかなりもめることになる。最初は全員がバラバラで攻撃をしたり守備をしたりというのを繰り返すのだが、時間を三十分で区切ってポジションを交代していくという全体を見た公平なルールでチームの結束を高めようとする。5チームのうち2チームが勝ち上がれるのだが、それに加えて下位であってもチーム内の得点王は一人だけ次のステージに進めるというルールが設定されている。主人公のチームが総当たり戦を勝ち残れるかどうかギリギリの順位になると、その中の一人が裏切って相手チームと共謀し自分が得点王になったあとで、相手側のチームの味方になりわざと負けようとする。この展開はルールの中で設定された個人とチームの報酬のジレンマの中で、ゲーム理論的に起こりうる人間模様という感じなのだが、この個人とチームという問題設定では面白いことにならない。ゲーム理論的にと書いたように、ルールがその場で起こりそうなことを決めてしまっていて他のサッカーと関係ない何かでも見たような展開なのだ。
ブルーロックは退屈なジレンマの次の試練に進む。そのルールは組みたい相手で三人チームをつくり、試合をしたい相手と三対三の試合をする。勝った方は相手チームから好きな選手を一人選んで自分の仲間にする。勝った方は四人チームになり、別の四人チームを探して試合をし、同じように勝つと一人引き抜きというのを続けて、五人対五人の試合に勝利すればその五人は次のステージに行ける。最初の三人対三人で負けて二人になったチームは同じように二人のチームを探して、勝ち三人に戻らなければならない。二人対二人で負けたチームで選ばれなかった方の選手は脱落になってしまう。
三対三や四対四のミニゲームでは、それぞれがフォワードでありディフェンダーでもある。前にあったような、ポジションの公平さのための組織的解決は必要ない。そして、このゲームでは勝つしかない。負けても相手に選んでもらえれば一人だけ助かることはできる。しかし、相手に選んでもらうためにはプレーで相手に評価されないといけないし、「わざと負けるから自分を選んで」というような展開は今後あるのかもしれないが(執筆中、22話「声」でそういうツッコミが入る)、今のところは別の楽しさがそういったゲーム外の策略を上回っているために見えてきていない。その楽しさとはこのアニメの中で化学反応と呼ばれているものだ。最初の試練では知らない誰かが選んだチームの中でポジションを回さざるをえなかった。その中で不満のあるものはチームで話し合って解決を見いだそうとすることもできるが、その見込みがないと思えば寄せ集めのチームに見切りをつけてサッカーの試合とは関係ないところで生き残ろうとすることができてしまう。次の試練では、自分の味方チームを自分で選ぶことができる。もちろん互いに合意すればだが。ブルーロックに集められた選手はドリブルやトラップなど、それぞれ一つは天才的な個性を持っていて、その自分の才能と他人の才能をかけ合わせると何が起こるか、次にどういうサッカーができるかを考えながら、試練を乗り越えていく。彼がいればチームが勝てる、新しいプレイの幅が広がるなど評価されれば選ばれるが、そうでなければ選ばれない。選手は監督ではないから、チームの全員を一つの方向に強制することはできない。一見すると意思疎通が取れていないようにも見えるが、だからこそ彼らは互いの才能を信じて、ほとんど互いの才能のみを手掛かりに次のパス、次のラン、次のシュートを繰り出し相手の予想してなかったようなゴール、化学反応を生み出すことができる。それは、『ぼっち・ざ・ろっく』でいうところのサプライズであり、『ひきこもり先生』でなされなかったようにみえる対話の可能性である。
コミュニケーションにハンデがあることの自覚 silent
主人公の青羽紬(あおば・つむぎ/川口春奈)は8年前に、一生をかけて愛したいと思えた恋人との別れを経験し、新たな人生を歩もうと前を向いて生きている一人の女性。そんな紬と大切な人との出会いは高校2年の秋、たまたま朝礼で耳にしたある男子生徒の声に惹(ひ)かれたことがきっかけでした。壇上で作文を読む、佐倉想(さくら・そう/目黒蓮)に心を奪われた紬は、次第に彼が気になる存在になっていることに気づきます。3年生で同じクラスとなり、共通の友人を通してだんだんと距離が縮まっていった二人は付き合うことに。音楽好きというお互いの趣味で通じ合い、仲を深めていった二人でしたが、卒業後のある日、これからも一緒にいたいと思う紬に対し、想は突然、理由も言わずに別れを告げて姿を消してしまいます。それから8年という月日が流れ、新たな人生を歩み始めていた紬でしたが、ある日、偶然、雑踏の中に想の姿を見かけたことをきっかけに、再び彼の存在を意識するようになっていきます。もう一度、想に会ってちゃんと話をしたいと彼の姿を探し始めた紬でしたが、実は彼が徐々に耳が聞こえにくくなる“若年発症型両側性感音難聴”を患い、聴力をほとんど失っていたという思いがけない現実を知ることになって…。
silent - フジテレビ
 |
| (<いよいよ6日(木)よる10時スタート>silent 予告 - YouTube) |
高校を卒業してから八年が経過して、佐倉想は耳が聞こえなくなっていた。そのことを知らずに青羽紬は彼と再会する。彼に後ろから話しかけても、少しも気づいてもらえない。やっと面と向かって話すことができる機会を得られても、紬は手話が分からないので向こうの伝えようとしていることがほとんど分からないし、紬の方から何かを伝えようとしても下手なジェスチャーでは思っていることを全然伝えることができない。ましてや彼らは高校時代につきあっていて、急に想の方から紬と一方的に別れ、かなり込み入った事情がある。彼らがそのことについてコミュニケーションしようとすると、なんとなくのジェスチャーやなんとなく伝えようでは伝えられることが全く足りない。
なんとなくで伝わらないコミュニケーションはどうしたら改善されるのか。登場人物のレベルでは、聞こえない想のために紬が手話を覚える。それがメインだが音声認識アプリや手書き、LINEなどのショートメッセージサービスも使われる。ただ、ドラマのなかのコミュニケーションは聴者と聾者の間だけで行われるのではなく、聴者と聴者の間でも会話があり、そこでも伝えることの難しさについてのちょっとした会話が行われる。紬が実家に帰った時に「実家に帰ると荷物が増える問題」について話す。紬の母は、言葉だけでは伝えるのは難しいから物にも託すのだという。母親は実家から家に戻る紬に、その日に作ったたくさんの料理などをタッパに入れてお土産としてわたす。
人と人との間を物が媒介する、という風に抽象化すると紬の母がわたしたようなお土産が画面を通して観客にもわたっていることに気づく。登場人物と観客の間を物が媒介する。最も分かりやすいのは、想と奈々の図書館のシーンだろう。奈々は想が聞こえなくなりはじめて人間関係を閉ざしていた頃に想に話しかけてきて支えてくれた人だ。奈々も耳が聞こえない。想は耳が聞こえなくなったことが受け入れられなかったが、奈々と出会って彼女から手話を習い覚えていく。二人はお互いに惹かれていくのだが、紬の登場や聴者と聾者の違いについて奈々が強く思っていることが二人の距離を縮めなくしてしまう。図書館で想と奈々はテーブルをはさんで向かい合って座っている。静かな図書館の中で彼らだけが騒がしく「話す」ことができる。このシンメトリーの構図の中で背景の本棚が彼らの関係を静かに暗示している。平行に置かれた本棚は中央の焦点に向かってまっすぐ伸びていくが、それは決して重ならない。奈々は手話を覚えたての想に「手話、下手だね」と笑っていう。想は「奈々に伝わればいい」という。
言語は言語しか相手にせず、そして突如として、意味に取り囲まれているのにふと気づくのである。
もしこれが本当だとすれば、言語の作用は絵画の作用とそう違ったものではない。一般に絵画は色彩や線などの沈黙の世界を通して私たちに到達し、私たちが持つ、言葉にならない解読の能力に訴えかけるのだが、この能力を制御できるのは、私たちがそれを盲目的に行使したり、作品を愛したりした後になってからである。(p109,110)
描くという行為は二つの面をもつ。一方で、キャンヴァスの一点に置かれた色彩の点や線があり、他方で、その全体における効果がある。両者を共通の尺度で測ることはできない。というのは、一つの点や線はほとんど無に等しいものでありながら、それだけで肖像や風景を変えてしまうからだ。(p110)
間接的言語と沈黙の声『精選シーニュ』モーリス・メルロ=ポンティ
他にも同じような例を見つけることができる。最後まで手話を覚えようとしなかった紬の弟の光が想の妹の萌から手話の本を借りて手話を覚えようとする。萌はすでに手話ができる。萌は階段で光に本を手渡すと一人で帰ろうとし、光が待ってと追いかけ、二人で階段を駆け上がっていく。居酒屋のシーン。居酒屋で奈々と奈々の昔の恋人(親友?)春尾正輝が話すシーンがあるのだが、最初は彼らはぎこちないがだんだん過去のすれ違いを解消して打ち解けていく。居酒屋のカウンター席の端に柱があるがこれがこのシーンの物である。最初はカメラが厨房から彼らをとらえて、その柱が彼ら二人の間に線が入っているように配置される。彼ら二人の間に距離があるように見える。彼らが打ち解けてくると、今度はカメラを客席側に置いて彼らをとらえる。そうすると、今まで二人の間にあった柱は後景に行ってしまって二人の間を邪魔するものが無くなっているように見える。この居酒屋のシーンでは、その二人で飲んでいるところに戸川湊斗という紬の元カレが加わってくるのだが、今いった奈々と春尾のカメラと柱の配置の切り替えを反復する。また、このシーンでは聾者の奈々と聴者だが手話のできる春尾、聴者で手話のできない湊斗の間で会話がなされ、奈々と湊斗の会話を春尾が通訳する。奈々と湊斗が話しているのだが、途中から奈々は湊斗に何かを言いながら、間接的に通訳の春尾に大事なことを伝えようとする。通訳は一種の媒介だが、人が物のように単純な物言わぬ媒介でないことが確認される。
この居酒屋でシーンの反復が表現されたが、ドラマ全体で同じことを何度か反復して伝えるメッセージを強めようとしている。例えば、耳が聞こえなくなった想と紬の関係は、過去の奈々と春尾の関係、奈々と想の関係の反復のようなものとして描かれる。それらは全く同じことを描いているわけではないが、聴者と聾者の出会いについてのいくつかの試行錯誤が想と紬の関係に繋がっていく。
言葉を喋っている人間の世界では、物を言わない事物は人間にくらべてずっと生気に乏しく、重要性をもたない。それらの事物は、第二級、第三級の生しか獲得しえない。それも事物を観察する人間が特別に明敏な感受力をもつ稀有な場合においてだけである。演劇では話している人間ともの言わぬ事物とでは色価に相違がある。両者は異なった次元に生きている。映画においてはこの価値の相違が消滅する。そこでは事物は演劇の場合のように軽視されないし格下げもされない。共に無声であることによって、事物は人間とほとんど同質になり、そのため生気と意味を獲得する。事物は人間に劣らず喋るので、そのため事物はじつに多くのことを言うのである。(p53)
『視覚的人間』ベラ・バラージュ
なんとなく伝わること、というのはつまりお互いにすでに知っていることだ。その内容について事前にお互いに理解がある。映画やドラマではなく、例えば話芸に目を向けてみれば、そこでは時事ネタ、古典的なネタ、家族ネタ、身内ネタ、下ネタ、あるあるネタなどあるあるが典型だが、そのことについて言葉が発せられれば、なんとなく状況が理解できるものが選ばれている。話芸の演者はほとんどの場合特別な衣装を着ていたり、特別な小道具を持ったり、特別な場所を選んだりしなくてもよい。そこでは相互理解が先取りされていて言葉だけで状況を想像させられるからだ。いわば省エネの表現である。それも一つの表現なのだが、『silent』で選ばれているのは他のアプローチ、かなり露骨な絵画表現や視覚表現である。画面から見えるものを「彼は~~した、彼女は~~した」といったような見なくてもわかる概念的な言語表現に置き換えられないようにすること、背景やそこに映っている人間を再び見えるようにすることである。このことは『silent』が特別にやっていることというわけではなく、最近見たドラマでは『なぜオ・スジェなのか』や『今日のウェブトゥーン』、『DOC』などでは自然にみられる。
 |
| (TVアニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」第2弾PV - YouTube) |

コメント